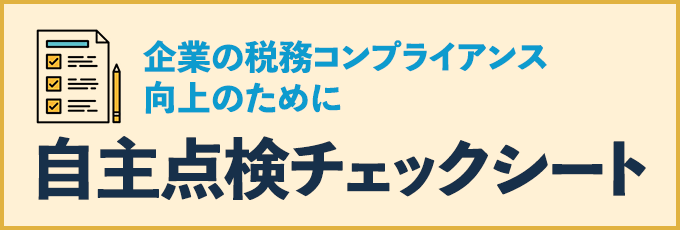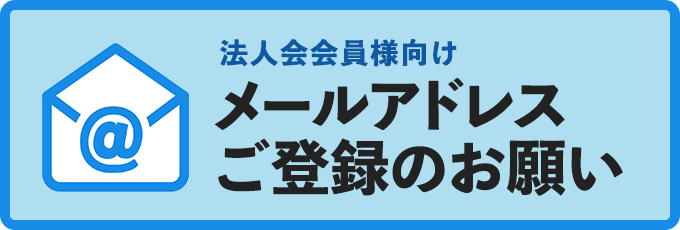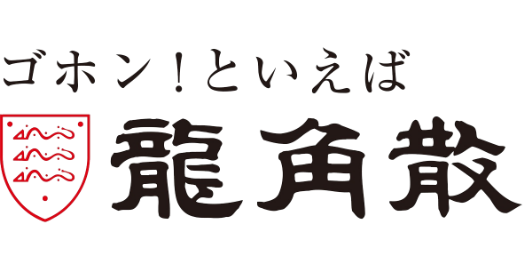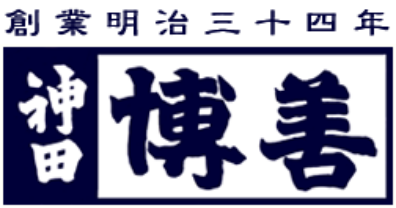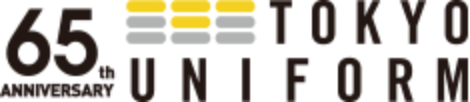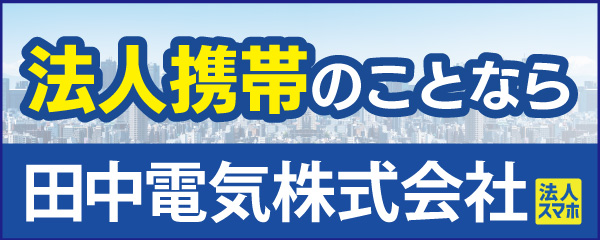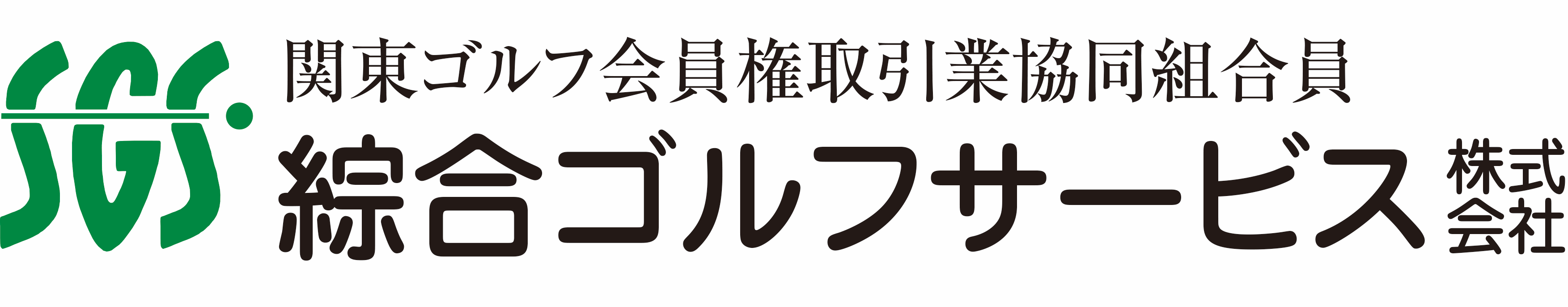お知らせ
2024.04.01
2024.04.01
2024.03.01
2024.03.01
2024.03.01
事業・研修のご案内
- 法人会会員だけでなく、一般の方にもご参加いただける研修・セミナーを開催しております。
- 申込フォームまたはFAX(03-3294-2500)でお申し込みいただけます。
| 開催日時 | 名称 | 会場 | 定員 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|
|
2024年05月09日(木) 13:30-16:30 |
令和6年 5月期 決算法人説明会 | 神田法人会2階セミナールーム ZOOMウェビナーを用いた集合&オンライン形式 |
会場:50名 ※1社2名まで オンライン:500名まで |
一般 神田法人会 会員 |
|
2024年05月23日(木) 14:00-16:00 |
令和6年度 源泉部会 公開研修会 | 神田法人会2階セミナールーム ZOOMウェビナーを用いた集合&オンライン形式 |
会場:60名 ※1社2名まで オンライン:500名まで |
一般 源泉部会員 神田法人会 会員 |
|
2024年05月29日(水) 14:00-16:00 |
令和6年度 税法実務研修会 | 神田法人会2階セミナールーム ZOOMウェビナーを用いた集合&オンライン形式 |
会場:50名 オンライン:500名まで |
一般 神田法人会 会員 |
|
2024年06月18日(火) 15:30-19:30 |
第12回 通常社員総会 | 学士会館 |
神田法人会 会員 |
|
| 直近の4件を表示しています | ||||
活動だより
神田法人会は
よき経営者をめざすものの団体です。
時代を先取りした経営を行うことが企業にとって大変重要なことです。
法人会の経営に関する研修会では、国税局や税務署担当官はじめ、専門の講師による最新の経営情報を提供するとともに、実践的な講習会、弁護士による法律相談も開催しています。
法人会の経営に関する研修会では、国税局や税務署担当官はじめ、専門の講師による最新の経営情報を提供するとともに、実践的な講習会、弁護士による法律相談も開催しています。
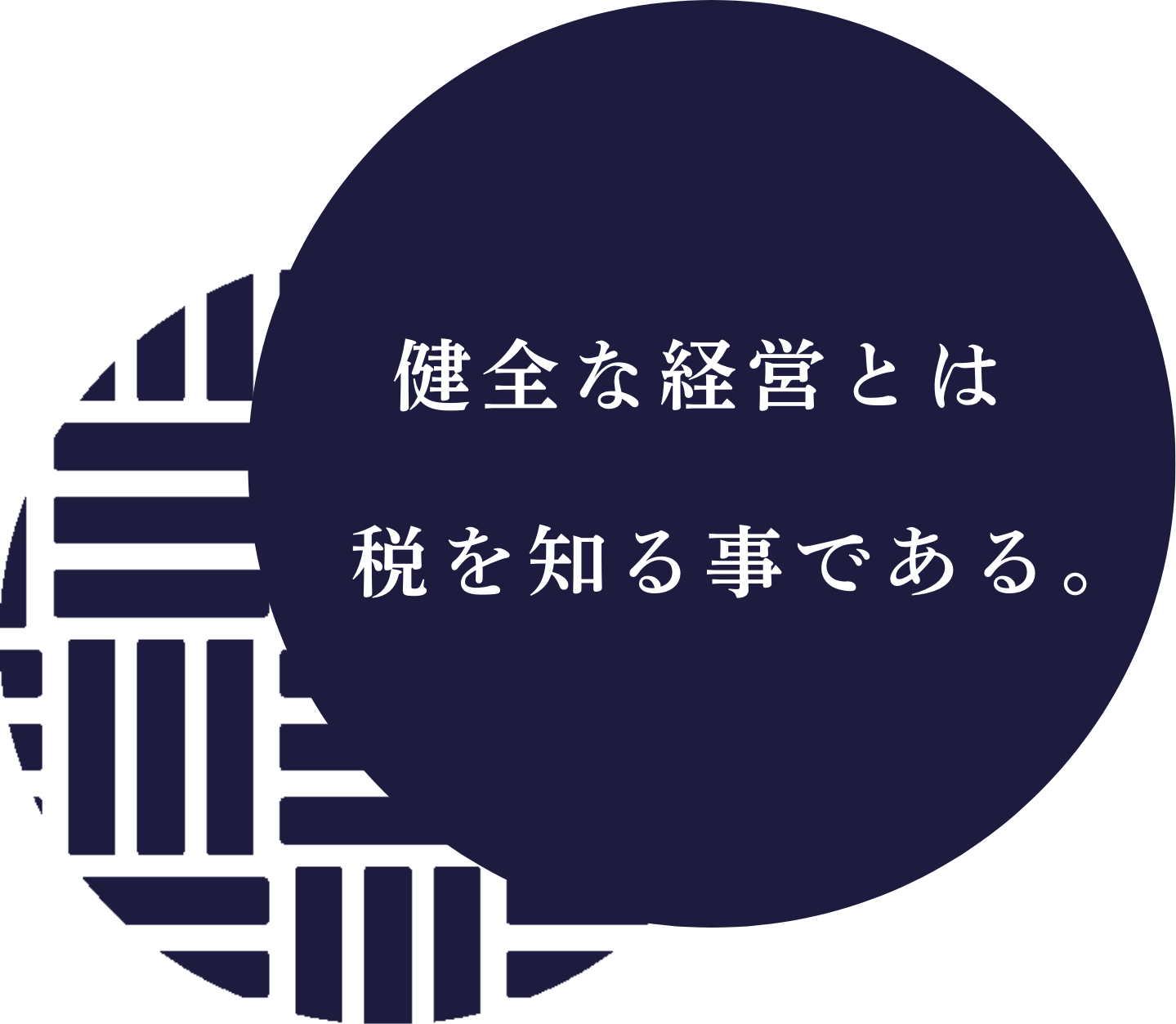
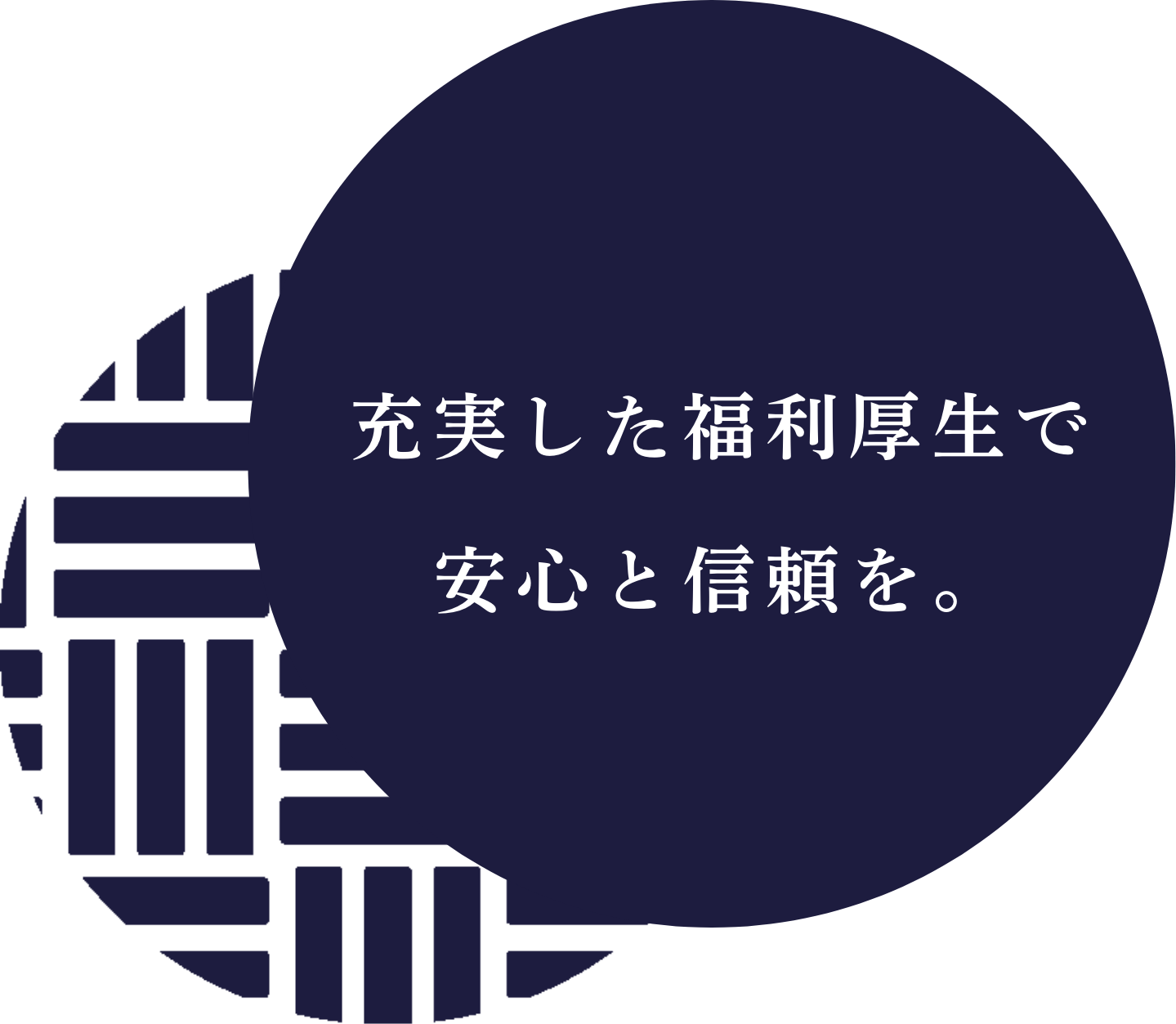
全国で約75万社のスケールメリットを活かした
さまざまな割引・共済制度で会員企業の福利厚生
法人会には、全国で約75万社の企業が加入しており、そのスケールメリットを活かしたさまざまな割引・共済制度で会員企業の福利厚生を幅広くサポートしています。